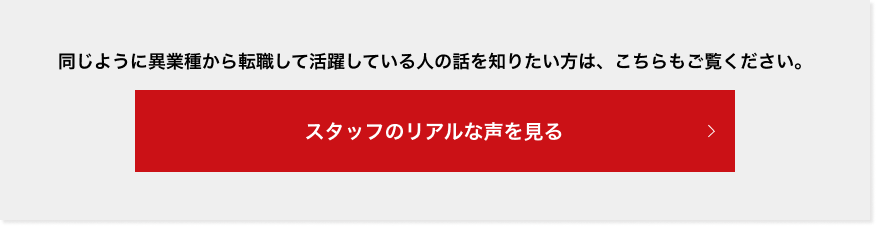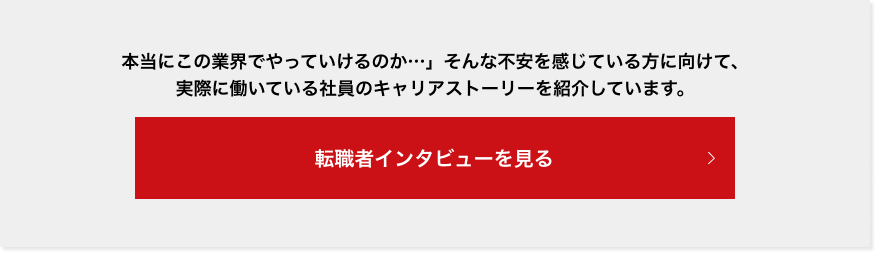色彩の知識は、デザイナーだけの専門領域ではありません。現代のインテリア業界においても、色彩構成は極めて重要なスキルとして位置づけられています。
しかし、美術やデザインの専門教育を受けていない方にとって、色彩構成は難しく感じられるかもしれません。特に、間違った色の組み合わせを選んでしまうと、空間全体の印象を大きく損なう可能性があります。
そこで今回は、インテリア業界で働く方や色彩検定の勉強を始めたい方に向けて、色彩構成のタブーと効果的なコツを詳しく解説します。これらの知識を身につけることで、プロフェッショナルとして自信を持って色彩提案ができるようになるでしょう。

目次
色彩構成の基本
色彩構成を理解するためには、まず色の基本的な性質を知ることが重要です。
色相
色相とは、赤、青、黄などの色の種類のことを指します。日常的に使っている「赤いシャツ」や「青いソファ」といった表現は、この色相による色の捉え方です。
色相は色相環(しきそうかん)という円形の図で表現され、隣り合う色は調和しやすく、向かい合う色(補色)は強いコントラストを生み出します。インテリアデザインでは、この色相の関係性を理解することが重要になります。
明度
明度とは、色の明るさと暗さを表す属性です。同じ赤色でも、明るい赤から暗い赤まで様々な明るさのバリエーションが存在します。
明度の違いを活用することで、空間に奥行きや立体感を演出できます。例えば、天井に明度の高い色を使用すると空間が広く感じられ、床に明度の低い色を使用すると安定感のある印象を作り出せます。
彩度
彩度とは、色の鮮やかさを表す属性で、派手な色と地味な色の違いを示します。高彩度の色は目を引きやすく活動的な印象を与える一方、低彩度の色は落ち着いた上品な雰囲気を演出します。
彩度を下げたい場合は、その色に黒やグレーを混ぜることで実現できます。
色彩構成でやってはいけないタブー
色彩構成において避けるべきタブーを理解することで、失敗のない配色を実現できます。ここでは、特に重要な3つのタブーをご紹介します。
色を多く使いすぎる
1つ目が、色を多く使いすぎる点です。「たくさんの色を使えば華やかで魅力的になる」という考えは、色彩構成における最大の落とし穴の一つです。
色を使いすぎると下記のような問題が起こりやすくなります。
- ・視覚的な混乱を招き、落ち着きのない空間になる
- ・各色の個性が相殺され、メリハリのない印象に
- ・後から調整や変更が困難になる
限られた色数で最大の効果を生み出すテクニックが重要です。
色の組み合わせが悪い
赤と緑、青とオレンジのような補色同士を等しい面積で使用すると、「色の競合」と呼ばれる現象が起こります。目がチカチカして疲労感を感じる、非常に不快な視覚効果です。
予防として下記を意識しましょう。
- ・等面積での使用は避ける
- ・どちらか一方を主色とし、もう一方を小面積のアクセントに
- ・明度や彩度を調整してコントラストを和らげる
- ・中間色を挟んで直接の対比を避ける
補色は適切に使用すれば空間に個性的な印象を与える優れた組み合わせですが、扱い方を間違えると逆効果になります。
場面に合わない色
色には強力な心理的効果があるため使用する空間の目的と色の特性が合わないと、居住者に不快感や違和感を与えてしまいます。
具体的には下記の通り。
- ・寝室で落ち着かない色を使用する
- ・レストランで食欲減退効果のある色を使用する
これらの問題が起きると、インテリアコーディネーターとしての信頼性を失う恐れがあります。色彩心理学は下記で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
色彩心理学とは?|資格取得のメリットと仕事への活かし方を紹介
色彩構成の考え方のコツ
成功する色彩構成には、理論に基づいた実践的なアプローチが必要です。ここでは、プロが実際に使用している手法をご紹介します。
基本比率を守る
インテリアデザインにおける配色の基本比率は、時代を超えて活用できるデザインテクニックです。この比率を守ることで、誰でも手軽にバランスの良い配色をまとめることができます。
| ベースカラー | 壁、床、天井などの大面積部分 |
| メインカラー | 家具、カーテンなどの中面積部分 |
| アクセントカラー | 小物、アートワークなどの小面積部分 |
色は最小限にする
シンプルな配色ほど失敗が少なく、洗練された印象を作り出せます。これは色彩構成における最も重要な原則の一つです。
例えば、白と黒、または白と赤だけの配色を見て、「バランスが悪い」「まとまりがない」と感じることはほとんどありません。しかし、そこに青や黄色などが混ざってくると、配色の難易度は一気に高くなります。2色以上使用する際は、次の方法で検討することをおすすめします。
- 1.まずは2色の組み合わせから始める
- 2.バランスが取れたら、慎重に第3の色を検討
- 3.各色の面積比率を意識して調整
- 4.全体の印象を客観的に評価
上記を意識して、失敗のリスクを最小限に抑えながら、美しい配色を実現しましょう。
色彩構成に関するよくある質問
色彩構成に関するよくある質問をまとめました。
色彩構成を活かせる職業は他にありますか?
色彩構成の知識は、多様な分野で活用できる汎用性の高いスキルです。
| 職種 | 活用場面 |
| インテリア業界 | 住空間の色彩提案 |
| デザイン業界 | 印刷物、製品、Webデザイン |
| 建築業界 | 外観や内装の色彩計画 |
| 美容業界 | メイクアップやヘアカラーの提案 |
| ファッション業界 | 服飾やアクセサリーの配色 |
特にインテリア関連職種では、色彩知識は必須スキルとして重視されています。
初心者が色彩構成を学ぶにはどうしたらいいですか?
色彩検定などの資格勉強から始めて見ると色彩の知識が身に付くのでおすすめです。
資格取得すれば専門知識を有している証明が手に入るので、将来、カラーコーディネーターとして活躍できるチャンスもあるかもしれません。
カラーコーディネーターとは?資格の難易度や色彩検定との違いを解説|ボーコンセプト・ジャパン採用サイト
まとめ
色彩構成は、適切な知識と実践によって必ずマスターできるスキルです。今回ご紹介した色彩構成のタブーを避け、プロが実践するコツを活用することで、インテリア業界でも自信を持って活躍できるでしょう。