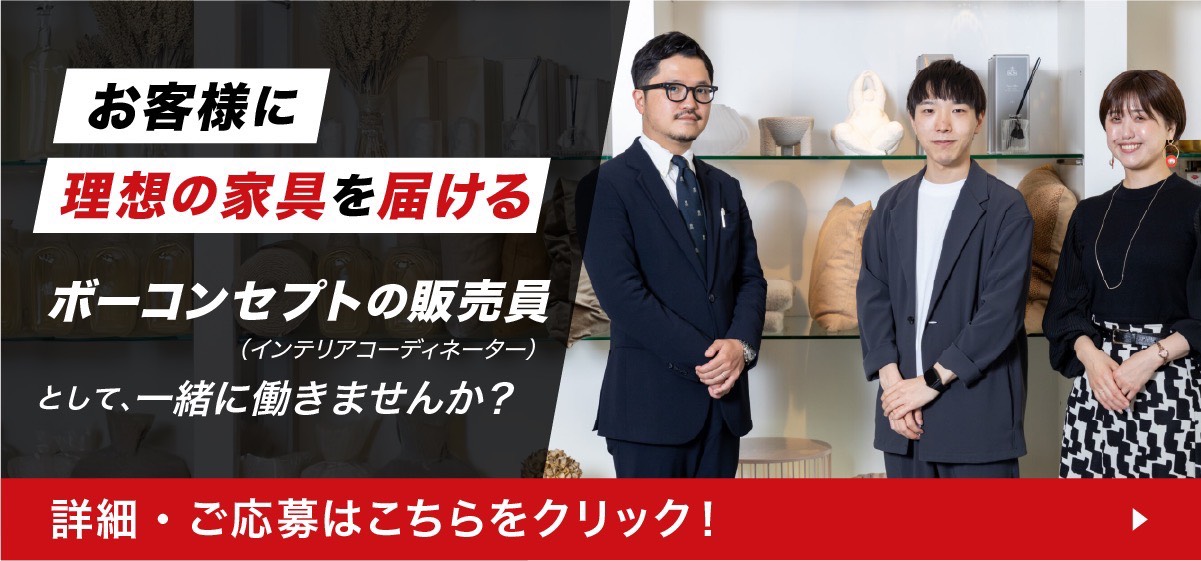色に関わる資格はいくつかありますが、代表的なものとしてカラーコーディネーターがあります。これからカラーコーディネーターの仕事に就きたいと考えている人なら、資格を取得して転職活動を有利に進められるメリットがあります。
カラーコーディネーター検定試験の受験を検討する際には、難易度や類似する資格との違いを把握しておくことが大切です。また、具体的な仕事内容や活躍できる業界などを把握しておきたいでしょう。本記事ではカラーコーディネーターについて、資格の難易度や色彩検定との違いなどを中心に解説していきます。

目次
カラーコーディネーターは、色に関する専門知識を備えている職業です。カラーコーディネーター検定という資格がありますが、資格の取得は必須ではありません。ただし、後述するように、資格取得すると収入面や業務面でメリットがあります。
では、カラーコーディネーターの仕事内容や仕事に就く方法について見ていきましょう。
カラーコーディネーターの仕事内容
カラーコーディネーターは、色に関するコンサルティングやコーディネートを全般的に行います。
個人の顧客に対して、ファッションやメイク、インテリアなどさまざまな場面において色に関するアドバイスを行います。また、法人の顧客に対して商品のコンセプトに合った色やその組み合わせなどをデザインの提案を行うことも多いです。
インテリア業界で活躍するカラーコーディネーターの業務内容や年収など、下記の記事で丸ごと解説しています。
内部リンク:「カラーコーディネーター なるには」
カラーコーディネーター検定とは
カラーコーディネーター検定は、東京商工会議所が実施している資格です。色に関する実践的な知識を学べる内容で、スタンダードクラスとアドバンスクラスに分かれています。
カラーコーディネーターの受験者は30代以下の若い年齢層が大半を占めているのが特徴です。
カラーコーディネーター検定の試験は年に2回実施され、IBT方式かCBT方式のどちらかを選択できます。IBT方式は自宅や勤務先のパソコンを使用して受験し、CBT方式は会場で受験します。
カラーコーディネーター検定の難易度
カラーコーディネーター検定の合格率は、スタンダードクラスが80%前後でアドバンスクラスは60%前後です。いずれも合格基準は100点満点中70点以上に設定されています。合格に必要な勉強時間の目安は、50~100時間程度です。
特にスタンダードクラスは、易しい内容の出題が中心で、きちんと勉強すれば大半の人は合格できます。アドバンスクラスもそれほど難しい内容ではありません。
カラーコーディネーター検定を受けるメリット
お客様からの信頼度が向上し、専門性の高いアドバイスを求められるケースが増えることで、自然と単価の高い案件を任されるようになります。
例えば、インテリア業界では一般的な接客業務から、より専門性を要求される色彩コンサルティング業務へとシフトすることで、基本給に加えて歩合給も大幅にアップする可能性があります。
カラーコーディネーターが活躍する業界

カラーコーディネーターはさまざまな領域で、色に関する専門知識を使って仕事をしています。カラーコーディネーターが活躍している業界について紹介します。
ファッション・アパレル業界
ファッションにおいて色の重要性は非常に高いです。デザインの形状が同じ衣服でも色の違いにより、印象は大きく異なります。トップスとボトムスの色の組み合わせや、小物との組み合わせなどを考える上でも色の専門知識を活かせます。
ファッションスタイリストを目指す人にも、カラーコーディネーターの資格はおすすめです。アパレルショップで働く販売員なら、顧客からアドバイスを求められることもあるでしょう。その際に色に関する専門知識を活かせます。
美容業界
美容師やネイリスト、メイクアップアーティストなどの職業でも、色に関する専門知識は強みです。例えば、ヘアカラーを選ぶ際に、顧客のイメージに合った提案ができます。メイクをする際には、顧客の肌の色を考慮して、微妙に違う色の使い分けもできるでしょう。
ネイルデザインにおいても、顧客のイメージに合わせて作るには、色の専門知識が必要です。
ブライダル業界
ブライダル業界では、ウェディングプランナーの仕事でカラーコーディネーターの資格を役立てられる場面が多いでしょう。
ウェディングプランナーは、結婚式会場における空間デザインの提案やセッティングから、ドレスやブーケのコーディネートもおこないます。色に関する専門知識を使い、顧客の希望に沿う提案やセッティングができます。
メーカー・広告・WEB業界
商品やサービスのブランディングにおいて、色は重要な要素です。
色が商品やサービスのイメージに直結し、色の違いが売れ行きに影響することもあります。マーケティングでは、商品のイメージを損なわない配色や消費者にインパクトを与えられる配色など、売上拡大のために必要な色の知識が求められます。
インテリア業界
インテリア業界では、家具選びや部屋の装飾などを考える際に、カラーコーディネーターが活躍します。個人宅はもちろんのこと、商業施設や医療機関、オフィスなど活躍の場が多いです。インテリア業界の主な勤務先は、インテリアショップや設計事務所、工務店などです。
北欧デンマークの家具を販売するボーコンセプトでは、セールスアソシエイト(販売員) およびストアマネージャー候補を募集しています。インテリア業界に興味のある方は下記ページより詳細をご覧ください。
【業界別】色彩に関する検定
カラーコーディネーター検定試験
工業業界で特に活躍する資格です。製品開発における色彩設計や、工業デザイン、インテリアコーディネーターの分野で重要視されます。
インテリア業界を目指すならこの資格が最もおすすめです。空間の色彩計画や照明との関係、素材との調和など、実務に直結する知識が体系的に学べます。
色彩検定
ファッション業界で働く際に力を発揮する資格です。元の名前である「ファッションカラーコーディネーター検定試験」のとおり、服に関する配色理論や、季節感を表現する色彩計画などが学べます。
アパレル業界での商品企画や販売業務で、専門的な色彩アドバイスができるようになり、顧客満足度の向上につながります。
色彩心理学についてご紹介しておりますので、ご興味がある方はご覧ください。
パーソナルカラーリスト検定
メイク・ファッション・ヘアカラーなど、似合う色をテーマに置いた検定で、比較的取得しやすい資格として人気があります。
美容業界やブライダル業界で個人向けコンサルティングを行う際に活用できるだけでなく、趣味と実益を兼ねた資格としても注目されています。
色彩士検定
デザイナー・アーティストが目指す資格です。芸術分野での色彩理論を深く学ぶことができます。試験は1級から3級まであり、3級から演習・実技が問われます。
カラーコーディネーター試験の概要
| 試験日程 | 6月・11月 |
| 受験資格 | 特になし |
| 試験時間 | 90分 |
| 受験料 | 【アドバンスクラス】7,700円(税込)
【スタンダードクラス】5,500円(税込) |
| 試験方式 | CBT(Computer Based Testing)方式 |
| 合格基準 | 70点以上(100点満点) |
スタンダードクラスは基礎的な色彩知識について問う試験で、その知識に加え、ビジネスで活用できる色彩知識を問う試験がアドバンスクラスです。
試験はパソコンを使用したCBT方式で実施されるため、全国の試験会場で都合の良い日時を選んで受験できます。
カラーコーディネーター検定の勉強方法
カラーコーディネーター検定の資格を取得したい場合には、環境などを考慮して自分に合った勉強方法を選ぶことが大切です。主に次のような勉強方法があります。
資格試験スクールに通う
資格試験スクールでカラーコーディネーター講座を受講する方法です。専門の講師による講義を受けられるため、効率良く学習できるのがメリットです。通学して学習する場合、モチベーションも維持しやすいでしょう。
ただし、人によっては自宅近くに資格試験スクールがない場合もあり、その場合にはオンラインスクールで受講する方法もあります。独学や通信講座と比べると、費用が高くなってしまうのが難点です。
通信講座を利用する
カラーコーディネーターの通信講座も多くあります。通信講座はスマホやPC、DVDなどで講義の動画を見て学習する方法です。自宅近くに資格試験スクールがなくても利用でき、時間に縛られずに好きなタイミングで学ぶことができます。
ただし、地道にコツコツ続ける必要があり、モチベーションの維持が大変です。資格試験スクールほどではないですが、受講に費用が発生します。
独学で学習する
カラーコーディネーター検定の公式テキストを購入して、独学で学習します。資格試験スクールや通信講座ほど費用は発生しません。時間を確保して勉強することができれば、独学でも無理なく合格できます。
通信講座以上にモチベーションの維持が大変ですが、できるだけお金をかけずに済ませたい人にはおすすめです。
まとめ
カラーコーディネーター検定は色に関する専門資格です。取得すればファッション・アパレル業界や美容業界、インテリア業界などさまざまな領域で活躍できます。仕事に就くのに資格は必須ではありませんが、資格取得はそれほど難しくはなく、きちんと勉強すれば合格できます。資格を取得すれば、転職活動を有利にすすめることができるでしょう。
未経験で色に携わる仕事に就きたい方は、カラーコーディネーター検定を取得して転職活動にのぞむのがおすすめです。
採用インフォメーション
北欧デンマークの家具を販売するボーコンセプトでは、現在セールスアソシエイト(販売員) およびストアマネージャー候補を募集しています。
仕事のミッションは、単に家具を販売するのではなくお客様の理想のライフスタイルの実現をお手伝いすることです。インテリアのトレンドやお客様の好みを踏まえてスタイリングを提案することも多いので、インテリアが好きな方ならきっとやりがいを持てるでしょう。
インテリア関連のお仕事に関心のある方は、ぜひ募集要項ページで詳しい仕事内容などをご覧ください。未経験の方も歓迎しています。
お客様にあわせて理想の空間をコーディネートする、インテリアデザインサービスの提供を行うセールスアソシエイトとして、一緒に働く仲間を募集しています。